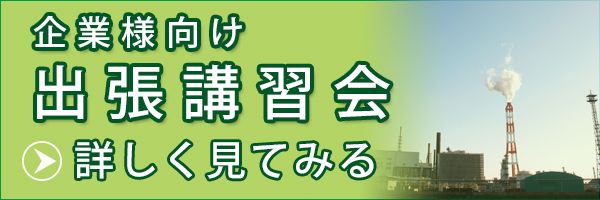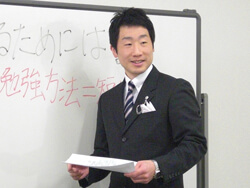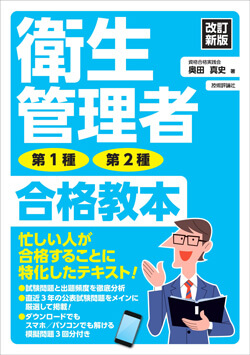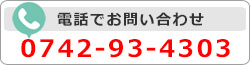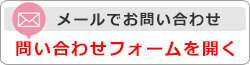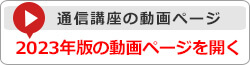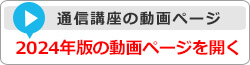衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2022年10月)
ここでは、2022年(令和4年)10月公表の過去問のうち「関係法令:一般(有害業務に係るもの以外のもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、特例第1種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2022年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2022年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2022年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2022年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2022年10月)
問1 事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
(1)常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2)常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
(3)常時50人以上の労働者を使用する燃料小売業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(4)2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
(5)衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、法定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答え(1)
(1)は誤り。各種商品小売業の事業場では、常時300人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
(2)は正しい。常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
(3)は正しい。燃料小売業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができます。
(4)は正しい。衛生管理者は、原則として事業場に専属の者から選任する必要があります。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができます。
(5)は正しい。衛生管理者の選任報告は、遅れることなく、所轄労働基準監督署に提出する必要があります。
問2 総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。
(2)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(3)総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
(4)総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(5)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。
(1)は誤り。総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければなりません。「準ずる者」は規定されていません。
(2)(3)(4)(5)は正しい。
問3 産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、産業医の選任の特例はないものとする。
(1)常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。
(2)産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
(3)事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
(4)事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
(5)事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。
答え(4)
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。代理者の選任は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者などについて規定されています。産業医では、代理者の選任は規定されていません。
働き方改革関連法の成立に伴い、改正労働安全衛生法が2019年4月1日から施行されました。
これにより長時間労働やメンタルヘルス不調などで、健康リスクが高い状況にある労働者を見落とさないため、産業医による健康相談や面接指導などが確実に実施されるための整備が図られました。
問4 労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
(1)自覚症状の有無の検査
(2)腹囲の検査
(3)胸部エックス線検査
(4)心電図検査
(5)血中脂質検査
(1)は省略できない。自覚症状の有無は、健康診断の必須項目です。
(2)(3)(4)(5)は省略できる。
問5 労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。
(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
(2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
(3)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
(4)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(1)は誤り。面接指導の基準時間は1か月当たり80時間超過が基準です。
(2)は正しい。タイムカード等で客観的な記録を取る必要があります。
(3)は誤り。面接指導の結果は、健康診断個人票ではなく、任意の様式に記載します。
(4)は誤り。医師の意見を聴くのは、遅滞なく行う必要があります。3か月以内ではありません。
(5)は誤り。面接指導の結果の記録を作成して、5年間保存しなければなりません。3年間ではありません。
問6 労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。
A 歯科医師
B 労働衛生コンサルタント
C 衛生管理者
D 公認心理師
(1)A,B
(2)A,D
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D
歯科医師と公認心理師が実施可能です。
労働衛生コンサルタントや衛生管理者は、心理的負担検査の実施者には含まれません。
問7 事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1)中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
(2)事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。
(3)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
(4)事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(5)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
(1)は誤り。空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、2か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければなりません。6か月ではありません。
(2)(3)(4)(5)は正しい。
問8 ある屋内作業場の床面から4mをこえない部分の容積が150m3であり、かつ、このうちの設備の占める部分の容積が55m3であるとき、法令上、常時就業させることのできる最大の労働者数は次のうちどれか。
(1)4人
(2)9人
(3)10人
(4)15人
(5)19人
答え(2)
まず、屋内作業場の使用可能容積を計算します。
使用可能容積=150m3-55m3=95m3
次にこの屋内作業場の最大労働者数を計算します。
気積(労働時に必要な最小の空間容積)は、労働者1人について、10m3以上でなければなりませんので、下記の様に計算します。
最大労働者数=95m3÷10m3/人=9.5人
小数点以下は切り捨てますので、(2)9人が正解です。
問9 労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
(1)時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(2)1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(4)妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。管理監督者等の場合であっても、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
問10 週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1)8日
(2)10日
(3)12日
(4)14日
(5)16日
答え(2)
週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満の労働者は、付与対象者の週所定労働日数に応じた年次有給休暇日数(比例付与日数)が付与されます。その計算式は、次のとおりです。なお、求めた日数の端数は切り捨てます。
比例付与日数=通常の労働者の付与日数×付与対象者の週所定労働日数÷5.2日
3年6か月継続勤務した通常労働者に対しては、14日の年次有給休暇が与えられます。
比例付与日数を計算すると次のようになります。
14日×4日÷5.2日 ≒10.77日
日数の端数は切り捨てますので、この労働者には、10日の年次有給休暇が与えられます。
したがって、(2)10日が正解です。
-
同カテゴリーの最新記事
- 2024/10/12:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2024年10月)
- 2024/04/30:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2024年4月)
- 2023/10/30:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年10月)
- 2023/04/30:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2023年4月)
- 2022/10/30:衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2022年10月)